薄明
ごじょうさとる×ふしぐろめぐみ
非公式二次創作ブログサイト
メイン
2023.09.04 23:12:40 編集
2026年3月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
2026年2月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
自室でごじょとそれなりに熱い夜を過ごした朝、教室でゆじとのばと顔を合わせたらちょっと気まずそうな顔でゆじに廊下に連れ出されて「…あのさ、…あー………声、聞こえてっから気をつけてな?」と言われて恥ずかしい申し訳ない気まずい恥ずかしいetcの大爆発で言葉を返せず固まるおめぐ。
お互いが初めての相手のため、実はおめぐの声が大きめだと気付いていなかったのである…!こんなもんなのかな、程度に思っていて、自室でする時は流石に隣の部屋に気をつけていたけれど、それじゃ足りない程度には大きめだったことを知り死ねるなら今死にたいおめぐ。固まっていたらごじょが授業のためにやってくるけれど、ゆじに知られた恥ずかしさとか申し訳なさ、自分の声の大きさと昨夜のことを思い出して顔が見れず、そのまま一日を終えることに。
そこからずーーーっと「俺って声でかいのか…」て悶々と悩み、「確かにあんあん言っては…いる…な……」と頭を抱え、目を合わせられないまま1週間くらいした頃にごじょに問い詰められることに。
もにょもにょごにょごにょと説明すると「…恵って声でかかったんだ…」と言いながらちょっと嬉しそうな顔。「…喜ぶところじゃない」「いや、みんなこんなもんなのかなって思ってたからさ、なんか嬉しくなっちゃった。へぇ〜〜〜……」「あんたが嬉しいなら、いいですけど……でももう俺の部屋じゃしませんからね」「悠仁に聞かれちゃったもんねぇ。抑えたつもりだったんだけどな」とかなんとか。なる、回
お互いが初めての相手のため、実はおめぐの声が大きめだと気付いていなかったのである…!こんなもんなのかな、程度に思っていて、自室でする時は流石に隣の部屋に気をつけていたけれど、それじゃ足りない程度には大きめだったことを知り死ねるなら今死にたいおめぐ。固まっていたらごじょが授業のためにやってくるけれど、ゆじに知られた恥ずかしさとか申し訳なさ、自分の声の大きさと昨夜のことを思い出して顔が見れず、そのまま一日を終えることに。
そこからずーーーっと「俺って声でかいのか…」て悶々と悩み、「確かにあんあん言っては…いる…な……」と頭を抱え、目を合わせられないまま1週間くらいした頃にごじょに問い詰められることに。
もにょもにょごにょごにょと説明すると「…恵って声でかかったんだ…」と言いながらちょっと嬉しそうな顔。「…喜ぶところじゃない」「いや、みんなこんなもんなのかなって思ってたからさ、なんか嬉しくなっちゃった。へぇ〜〜〜……」「あんたが嬉しいなら、いいですけど……でももう俺の部屋じゃしませんからね」「悠仁に聞かれちゃったもんねぇ。抑えたつもりだったんだけどな」とかなんとか。なる、回
昔は怒らすと渾を呼び出して横にべったり貼り付けさせてごじょを近寄らせないように威嚇してて「意味ないの分かってやってんのかわい♡」「先生また怒らせたの?」「いい加減にしなさいよ」なんてくらいのもんだったんだけど、時が流れめぐちゃん先生にもなると家の中をまこらくんの腕に抱えられながら移動して近寄ったら殺すってオーラを発するようになる。「やばいやばいやばい恵めちゃくちゃ怒ってる家の中まこらに乗って移動してる怖すぎる」『先生、いいから早く謝りな?』「な、何にここまでブチ切れてるのか分かんない…心当たりがありすぎて……」『んー…自業自得ってやつだね』『私らに電話する前に伏黒に土下座しに行け』
#めぐちゃん先生
#めぐちゃん先生
五伏いちゃラブえっち過激派
2026.02.09 03:31:11 編集
Powered by てがろぐ Ver 4.2.0.






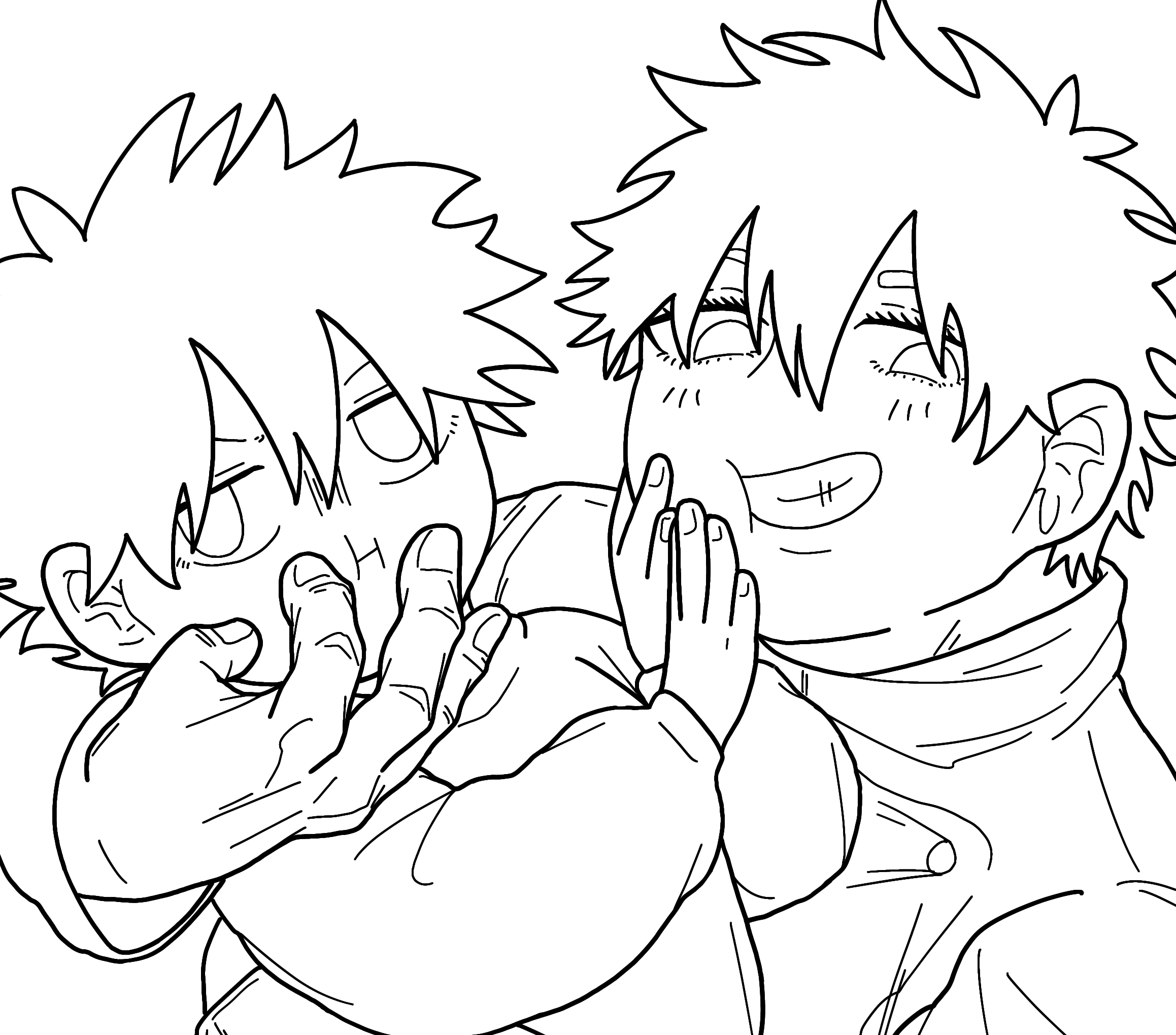




過去絵:2020~21 /2022 /2023 /2024 /2025 /2026
(最終更新26.2.27)
____
←旧 新→
小説:忘れ形見/朝露と共に消えていくもの/閑話休題/スリーピングビューティー(R18)/きらきらぼし/明日はソファを買おう。(R18)/「褒めて!」(R18)/愛を知ってしまった僕たちは呪われてしまった/グッバイオールドブルー/麦茶素股(R18)/今日はポイント3倍デー(R18)
SS:お風呂/目隠し/七海と飲み会/弔い/歯型/ひっつき虫in夏/彼岸/向日葵(伏)(五)/夏祭り/隣がいない夜/恵の部屋で(R18)/呼び声/ハンドクリーム/ホットケーキ/薬指/性欲/喧嘩/人魚の夢/こたつみかん/寝正月(R18)/彼シャツトレンカ(R18)/危機感/深爪、ダメ絶対/長い夜/そのくらいの我儘、/モーニングルーティン/知らぬが仏/待ち合わせ/逢いたい/さみしい2人/今際/うなじ/つむじ/私は察しのいい女/セックスの仕方/散髪/プロポーズ/明晰夢/お説教/大人向けコーナー/誘い下手/それって結構愛じゃない?/よしよしわふわふ/盛り上がった朝/愛が重い/ビッグベイビー/ふたごたまご/早寝遅起き/偏頭痛(五)/キュートアグレッション/暑さ対策/自慢したがり/不器用/名前だけの星/フラッシュバック(R18)/エチケット/形の遺るもの/天変地異/酔っ払い/待ちきれないのはお互い様/芽生え/ナンパごっこ/偏頭痛(伏)/かき氷/飴玉スーパーブルームーン/悪い夢/ココア/いんがおうほう/元旦/リベンジ/合わせる顔がない/ご都合呪いに気をつけて(R18)/花束を私から貴方へ/ごじょ誕2024/伏黒恵専用スマホスタンド/子猫の甘噛み/山なし落ちなしむっつりさん/ひとりごと/まんまる虫/香水/リッチな特別コーヒー/パプリカ/反省の弁は要らない/今日はそういう日/つまりは惚れた弱み/僕の恵ってえっちだ/麦茶といたずら/確信犯と横着者/夏の風物詩/小説より奇なり/内緒の話/匂わせ/うたた寝、冷めたコーヒー/はじめての/共に過ごすということ
自分用柊英まとめ